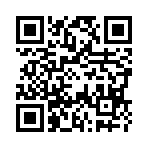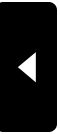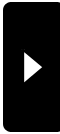スポンサーサイト
貴方だけのメンテパックを提案する
2015年12月30日
メンテナンスパックなどというと、ディーラーの十八番のように見えるが、そうではない。
むしろ、モータース店が積極的に扱っていくべき商品である。
クルマを売っていないから、とか商品化ができないなどが
モータース店が扱ていない大方の理由だ。
ご承知のように、メンテナンスパックは、1年間とか2年間に必要ないくつかの定期交換部品や、
点検などをパッケージにしたものだ。価格が安くなるなど客のメリットも多い。
販売する側も、1年間とか2年間のメンテナンスを一度の契約で販売することができるので、
販売コストが下がるし、事前に代金を一括受けとることができるなど、メリットがある。
だから、ぜひモータース店でも積極的販売をしていってほしいVAS 5054A 日本語。
メンテナンスパックは、販売してしまったら、後は期日到来に合わせてメンテナンスを実施
するものと思っていたら大きな間違いだ。

地域密着経営をしていこうとしているのであれば、なおさらなのとである。
同じ商品でも、クルマの使用ケースや契約時の走行距離数、過去のメンテナンス内容などから
メンテナンスの実施時期を決めなくてはならない。
それが、地域密着型のメンテナンスパックの販売なのだ。
契約が済んだら、まずやるべきことはメンテナンスの実施時期を、お客と相談しながら
決めていく。走行距離が多いお客には、オイル交換などを追加で購入いただくといい。
当然、特別割引価格で提供することになる。
〇〇様、月間の平均走行距離数が〇〇キロですから、オイル交換は〇月と〇月に実施したほうが
よろしいかと思いますが、いかがでしょうか、といった具合である。
ワイパーラバーは、現在の損耗ですと〇月ごろが交換時期になるかと思われます。交換は〇月で
よろしいでしょうかDigiprog 3。
このよいうにして、パックのメンテナンス内容に沿って、実施時期を決めていく。決まった実施
時期は、一覧表にしてお客さまに渡すこと。
個客に密着したメンテナンス実施を作ることによって、より高い安全であり、安心を提供できる。
また、エコにも効果的である。
半年ごとに自動的に実施時期を決めるのは、お客を「量」でしか見ていないのと同じだ。
十人十色、それによって内容を決める。ぜひこのようなメンテナンスパックを販売してほしい。
2015.7 BMW ICOM A2+B+C 診断&プログラミングツール
周知徹底する
むしろ、モータース店が積極的に扱っていくべき商品である。
クルマを売っていないから、とか商品化ができないなどが
モータース店が扱ていない大方の理由だ。
ご承知のように、メンテナンスパックは、1年間とか2年間に必要ないくつかの定期交換部品や、
点検などをパッケージにしたものだ。価格が安くなるなど客のメリットも多い。
販売する側も、1年間とか2年間のメンテナンスを一度の契約で販売することができるので、
販売コストが下がるし、事前に代金を一括受けとることができるなど、メリットがある。
だから、ぜひモータース店でも積極的販売をしていってほしいVAS 5054A 日本語。
メンテナンスパックは、販売してしまったら、後は期日到来に合わせてメンテナンスを実施
するものと思っていたら大きな間違いだ。

地域密着経営をしていこうとしているのであれば、なおさらなのとである。
同じ商品でも、クルマの使用ケースや契約時の走行距離数、過去のメンテナンス内容などから
メンテナンスの実施時期を決めなくてはならない。
それが、地域密着型のメンテナンスパックの販売なのだ。
契約が済んだら、まずやるべきことはメンテナンスの実施時期を、お客と相談しながら
決めていく。走行距離が多いお客には、オイル交換などを追加で購入いただくといい。
当然、特別割引価格で提供することになる。
〇〇様、月間の平均走行距離数が〇〇キロですから、オイル交換は〇月と〇月に実施したほうが
よろしいかと思いますが、いかがでしょうか、といった具合である。
ワイパーラバーは、現在の損耗ですと〇月ごろが交換時期になるかと思われます。交換は〇月で
よろしいでしょうかDigiprog 3。
このよいうにして、パックのメンテナンス内容に沿って、実施時期を決めていく。決まった実施
時期は、一覧表にしてお客さまに渡すこと。
個客に密着したメンテナンス実施を作ることによって、より高い安全であり、安心を提供できる。
また、エコにも効果的である。
半年ごとに自動的に実施時期を決めるのは、お客を「量」でしか見ていないのと同じだ。
十人十色、それによって内容を決める。ぜひこのようなメンテナンスパックを販売してほしい。
2015.7 BMW ICOM A2+B+C 診断&プログラミングツール
周知徹底する
コンバージョンEVの課題
2015年12月17日
ガソリン車をEVに改造する作業自体は、さほど難しくない。高度な改造をしない限り
慣れることで解決できることが多い。
ビジネス化に向けての課題は、作業以外のところにある。
一つは、価格の問題である。軽自動車の新車が一台買えるほどの改造費では、
改造需要は高まらない。
趣味で今まで来たのもこうしたことが課題であったことは想像に難くない。
日本EVクラブを見てもそのことが見て取れる。旧車で希少価値があるクルマを
永く愛着を持って乗りたいオーナーが、EVに改造している。
一般のオーナーが100万円を超える改造費を、懐からそうやすやすとは出さない。
出すためには、50万円、できれば30万円台で改造できることだ必要だろう。
そのためにも改造キット全体を低価格化することと、新車EVに国(補助金=基準額の二分の一)や
地方自治体などからの補助金が受けられる、コンバージョンEVも同じような制度が必要だ。
新車を製造するには、CO2は嫌でも排出するが、保有車両は製造すみだからCO2は基本的に
「0」であるからして、新車よりもよほど環境にやさしい。こうしたことを十分に加味して、早く補助金
制度を設けてほしいものだ車電気テスター。
補助金の額を決めるのは、改造にかかる基準額を決めることと、補助率を決める
二つを解決しなければならないが、補助率はともかくとして、基準額を決めることが
難しいとは思うが、車種ごとに基準額を固定にすることもできるので、早く制度作りに動いてほしい。
改造キットで半分以上をバッテリーが占める。したがって、バッテリーの価格は絶対に下げる必要が
ある。これは、新車EVの普及などによって、大幅に下がると予想されているし、場合によっては
海外製品を使うことで対応できると思われる。
現に、国産では300万円以上するリチュームイオン電池が中国産では100万円を切る価格に
なっているという。品質がどの程度か分からないが、競争原理が働くだろうから、ここ数年、
遅くとも5年以内には相当低価格になるだろう。
次の課題は、対象車両だ。
現在多くの改造に使われているのが「MT車」、マニュアルミッション車なのだ。AT車でも
いいのではないかと思うが、これが難しい。

モーターの特性によるのだ。モーターは始動するとトルクがすぐに高くなるが、モーターの
回転が速くなってくると、回転と比例してトルクが下がってくる。
ところが、ATは回転が速くなるとシフトアップする。モーターの特性上、シフトアップしては困るのだ。
下り坂ならともかくも、少々の登り坂になると走らなくなってしまう。
では、ATを取り外してドライブシャフトと直結にしてしまうという発想もできるが、FF車はそれができない。
FR車であれば、改造できないこともないが、苦労する。
こうしたことの解決策としては、インホイールモーターを使う手がある。
しかし、今現在はこのモーターつ使ったキットが販売されていないこともあるし、内輪と外輪差を制御する
技術が難しく、改造に向くか疑問があるという。
次に、バッテリーの重要配分が課題になる。鉛バッテリーだと一個20kgもするものを8個から10個積み込む。
合計で160kgから200kgにもなる。なんと大人2.5人から3人強を積んで走ることになる。
これだけの重量をトランクに積めば、クルマの重量バランスが崩れて、ハンドル操作が難しくなる。
また、リヤの足回りを強化しなかればならないこともある。そうならないためには、バッテリーを積む
場所を考えて、改造しなければならない。当然、日頃のメンテナンスのことも考慮する必要がある。
改造車に軽の1BOX車が多いのは、バッテリーを積む込むスペースが確保しやすいために
選ばれているのだOBD2アダプター。
もう一つ課題がある。これはバッテリーになるのだが、重量の面ではなく、バッテリー容量による
航続距離が課題なのだ。鉛バッテリーで8個積んでも、50km程度である。同じだけリチュームイオン電池を
にすると目が飛び出るほど高額なってしまう。価格のことを考えると「鉛バッテリー」が現実的である。
ヒーター、エアコンなどの快適ドライブに欠かせない電装品を使用して走行しすると、当然航続距離は
短くなってしまう。アイミーブでも、カタログ上の航続距離は160kmとなっているが、ヒーターなどを
使用しながら走行すると、80km程度しか走れないという。
まあ、幼稚園の送迎や日用品の買物などで使うには、80kmも走れれば御の字だと思う。
それでもいざとなったときのことを考えると、100kmは欲しいところだ。EVに関する意識調査では、
走行距離の短さよりも値段に関心が高いという結果もあり、50kmは、我慢の限界で許容範囲ともいえる。
CO2の排出量、燃料費では、EVは他のHVやPHVなどの次世代自動車の中では、抜群の優等生である。
したがって、EVはHV、PHVに代わって次世代自動車の主役になれるものと思う。
そうした時代を見据えて、今からコンバージョンEVの備えをしておくことが必要だろう。
BMW X6 SUV複数障害のダッシュボードのライトが点滅
立会い説明の要領
慣れることで解決できることが多い。
ビジネス化に向けての課題は、作業以外のところにある。
一つは、価格の問題である。軽自動車の新車が一台買えるほどの改造費では、
改造需要は高まらない。
趣味で今まで来たのもこうしたことが課題であったことは想像に難くない。
日本EVクラブを見てもそのことが見て取れる。旧車で希少価値があるクルマを
永く愛着を持って乗りたいオーナーが、EVに改造している。
一般のオーナーが100万円を超える改造費を、懐からそうやすやすとは出さない。
出すためには、50万円、できれば30万円台で改造できることだ必要だろう。
そのためにも改造キット全体を低価格化することと、新車EVに国(補助金=基準額の二分の一)や
地方自治体などからの補助金が受けられる、コンバージョンEVも同じような制度が必要だ。
新車を製造するには、CO2は嫌でも排出するが、保有車両は製造すみだからCO2は基本的に
「0」であるからして、新車よりもよほど環境にやさしい。こうしたことを十分に加味して、早く補助金
制度を設けてほしいものだ車電気テスター。
補助金の額を決めるのは、改造にかかる基準額を決めることと、補助率を決める
二つを解決しなければならないが、補助率はともかくとして、基準額を決めることが
難しいとは思うが、車種ごとに基準額を固定にすることもできるので、早く制度作りに動いてほしい。
改造キットで半分以上をバッテリーが占める。したがって、バッテリーの価格は絶対に下げる必要が
ある。これは、新車EVの普及などによって、大幅に下がると予想されているし、場合によっては
海外製品を使うことで対応できると思われる。
現に、国産では300万円以上するリチュームイオン電池が中国産では100万円を切る価格に
なっているという。品質がどの程度か分からないが、競争原理が働くだろうから、ここ数年、
遅くとも5年以内には相当低価格になるだろう。
次の課題は、対象車両だ。
現在多くの改造に使われているのが「MT車」、マニュアルミッション車なのだ。AT車でも
いいのではないかと思うが、これが難しい。

モーターの特性によるのだ。モーターは始動するとトルクがすぐに高くなるが、モーターの
回転が速くなってくると、回転と比例してトルクが下がってくる。
ところが、ATは回転が速くなるとシフトアップする。モーターの特性上、シフトアップしては困るのだ。
下り坂ならともかくも、少々の登り坂になると走らなくなってしまう。
では、ATを取り外してドライブシャフトと直結にしてしまうという発想もできるが、FF車はそれができない。
FR車であれば、改造できないこともないが、苦労する。
こうしたことの解決策としては、インホイールモーターを使う手がある。
しかし、今現在はこのモーターつ使ったキットが販売されていないこともあるし、内輪と外輪差を制御する
技術が難しく、改造に向くか疑問があるという。
次に、バッテリーの重要配分が課題になる。鉛バッテリーだと一個20kgもするものを8個から10個積み込む。
合計で160kgから200kgにもなる。なんと大人2.5人から3人強を積んで走ることになる。
これだけの重量をトランクに積めば、クルマの重量バランスが崩れて、ハンドル操作が難しくなる。
また、リヤの足回りを強化しなかればならないこともある。そうならないためには、バッテリーを積む
場所を考えて、改造しなければならない。当然、日頃のメンテナンスのことも考慮する必要がある。
改造車に軽の1BOX車が多いのは、バッテリーを積む込むスペースが確保しやすいために
選ばれているのだOBD2アダプター。
もう一つ課題がある。これはバッテリーになるのだが、重量の面ではなく、バッテリー容量による
航続距離が課題なのだ。鉛バッテリーで8個積んでも、50km程度である。同じだけリチュームイオン電池を
にすると目が飛び出るほど高額なってしまう。価格のことを考えると「鉛バッテリー」が現実的である。
ヒーター、エアコンなどの快適ドライブに欠かせない電装品を使用して走行しすると、当然航続距離は
短くなってしまう。アイミーブでも、カタログ上の航続距離は160kmとなっているが、ヒーターなどを
使用しながら走行すると、80km程度しか走れないという。
まあ、幼稚園の送迎や日用品の買物などで使うには、80kmも走れれば御の字だと思う。
それでもいざとなったときのことを考えると、100kmは欲しいところだ。EVに関する意識調査では、
走行距離の短さよりも値段に関心が高いという結果もあり、50kmは、我慢の限界で許容範囲ともいえる。
CO2の排出量、燃料費では、EVは他のHVやPHVなどの次世代自動車の中では、抜群の優等生である。
したがって、EVはHV、PHVに代わって次世代自動車の主役になれるものと思う。
そうした時代を見据えて、今からコンバージョンEVの備えをしておくことが必要だろう。
BMW X6 SUV複数障害のダッシュボードのライトが点滅
立会い説明の要領
H21年度分解整備事業実態調査緊急レポート(3)気になる工賃売上
2015年12月04日
整備売上でもう一つ見ておかなければならないのが「品目別売上」だ。品目とは、工賃、部品、外注のことである。
この3品目が整備売上の内訳である。この3品目の売上構成によって、粗利益率が変わってくるので、注意しておきたい売上である。
業態別の品目別構成比は、以下のとおりであるホンダ診断機。
・専業工場⇒ 工賃52.5% 部品35.3% 外注12.2%
・整備兼業⇒ 工賃46.7% 部品37.8% 外注15.8%
・ディーラー⇒工賃43.7% 部品38.9% 外注17.4%
この構成比を前年度比べてみると
・専業工場⇒ 工賃-10.6% 部品+15.0% 外注+15.1%
・整備兼業⇒ 工賃-0.4 % 部品-15.6% 外注+5.4 %
・ディーラー⇒工賃+10.8% 部品-3.2 % 外注-13.4%

専業工場では、工賃売上構成比が前年は58.7%だったものが、本年は52.5%となり、実に伸び率では二桁のマイナスである。工賃売上構成比が減った分、部品及び外注の構成比が高まった。デイーラーはその逆で、工賃売上構成は前年よりも10.8%も伸ばした。
この結果、粗利益率は以下の通りとなった。
・専業工場⇒ 62.7%(前年比-8.1%)
・兼業工場⇒ 58,9%( 同 -2.6%)
・ディーラー⇒61.8%( 同 +5.6%)
専業工場は、売上の減少額は工場平均でマイナス6,089千円(前年比ー14.4%)、粗利益額はマイナス5,985千円(-21.4%)の減少となった。この粗利益額は、整備要員の年間給与の1.7人分(一人当たり3,469千円)に相当する額が減少したことになる。
整備要員の労働分配率は56.8%である。他に使える割合が43.2%しかないことになり、よほど物件費を切り詰めないと、営業赤字または経常赤字になる確率が高くなっている。
したがって、コスト体質をそのままにして、価格競争に加わってはならないのだ。価格競争に加わる資格は、コストの削減が先に達成できてからのことになるDigiprog III V4 94。
コスト削減の対象は、「人件費」がまず挙げられる。固定的な賃金制度から変動的な賃金制度、いわゆる成果配分型の賃金制度への移行の検討だ。
また、正社員から臨時社員の検討も必要だろう。
次に、工場経費の見直しだ。特に、工場消耗品を見直してほしい。加えて、在庫経費の削減である。在庫部品、オイル類の在庫、塗料関係の在庫だ、安い時に大量に仕入れるようなことは、止めるべきである。必要な時に必要な量だけを仕入れる。義理や人情に負けれはダメ。
そして、作業時間の短縮である。一台の作業時間を10分縮めたら年間で短縮できる時間は莫大な量になる。一度計算してみてほしい。たかが10分などと思っているようでは、価格競争に勝利することはできない。
価格競争とは、体力競争でもある。大飯ぐらいのコスト体質であれば、スリムにしていかなればならないのだ。
AAに頼らないこと
Audi VW VAG K+CAN COMMANDER 3.6車両診断機
この3品目が整備売上の内訳である。この3品目の売上構成によって、粗利益率が変わってくるので、注意しておきたい売上である。
業態別の品目別構成比は、以下のとおりであるホンダ診断機。
・専業工場⇒ 工賃52.5% 部品35.3% 外注12.2%
・整備兼業⇒ 工賃46.7% 部品37.8% 外注15.8%
・ディーラー⇒工賃43.7% 部品38.9% 外注17.4%
この構成比を前年度比べてみると
・専業工場⇒ 工賃-10.6% 部品+15.0% 外注+15.1%
・整備兼業⇒ 工賃-0.4 % 部品-15.6% 外注+5.4 %
・ディーラー⇒工賃+10.8% 部品-3.2 % 外注-13.4%

専業工場では、工賃売上構成比が前年は58.7%だったものが、本年は52.5%となり、実に伸び率では二桁のマイナスである。工賃売上構成比が減った分、部品及び外注の構成比が高まった。デイーラーはその逆で、工賃売上構成は前年よりも10.8%も伸ばした。
この結果、粗利益率は以下の通りとなった。
・専業工場⇒ 62.7%(前年比-8.1%)
・兼業工場⇒ 58,9%( 同 -2.6%)
・ディーラー⇒61.8%( 同 +5.6%)
専業工場は、売上の減少額は工場平均でマイナス6,089千円(前年比ー14.4%)、粗利益額はマイナス5,985千円(-21.4%)の減少となった。この粗利益額は、整備要員の年間給与の1.7人分(一人当たり3,469千円)に相当する額が減少したことになる。
整備要員の労働分配率は56.8%である。他に使える割合が43.2%しかないことになり、よほど物件費を切り詰めないと、営業赤字または経常赤字になる確率が高くなっている。
したがって、コスト体質をそのままにして、価格競争に加わってはならないのだ。価格競争に加わる資格は、コストの削減が先に達成できてからのことになるDigiprog III V4 94。
コスト削減の対象は、「人件費」がまず挙げられる。固定的な賃金制度から変動的な賃金制度、いわゆる成果配分型の賃金制度への移行の検討だ。
また、正社員から臨時社員の検討も必要だろう。
次に、工場経費の見直しだ。特に、工場消耗品を見直してほしい。加えて、在庫経費の削減である。在庫部品、オイル類の在庫、塗料関係の在庫だ、安い時に大量に仕入れるようなことは、止めるべきである。必要な時に必要な量だけを仕入れる。義理や人情に負けれはダメ。
そして、作業時間の短縮である。一台の作業時間を10分縮めたら年間で短縮できる時間は莫大な量になる。一度計算してみてほしい。たかが10分などと思っているようでは、価格競争に勝利することはできない。
価格競争とは、体力競争でもある。大飯ぐらいのコスト体質であれば、スリムにしていかなればならないのだ。
AAに頼らないこと
Audi VW VAG K+CAN COMMANDER 3.6車両診断機
売上の3要素から見た来年の経営課題!
2015年11月21日
奈良県の整備商工組合が実施した「労働環境実態調査」結果を見ると、654組合員の7割以上が収益が減少した回答した。そのうち、何と収益が減少した原因の62%が管理顧客の減少と回答している。
それを踏まえて、今後の経営の重点課題は何かと聞いたところ、
第一位:新規客の開拓(47%)
第二位:営業力の向上(30%)
第三位:優秀な人材の確保(21%)
第四位:技術力の向上(20%)
第五位:従業員の能力開発(15%)
同 :生産性の向上(15%)
となっている。
売上アップの命題に対する答えの第一位が「新規客の開拓」を挙げている。減った管理客を補充するために、新規客の開拓が必要と考えていることになる。売上は、単純に「量×単価」で求められるから、要素の一つである「量」を増やすことは当然であるBMW診断機。
しかし、チョット安直過ぎてはいないだろうか。むしろ、減った理由を改善すべきことが第一位に来るのが本来ではないだろうか。水漏れしている器に、何ぼ水を継ぎ足しても器は満杯にはならない。

水を満杯にするには、まず漏れているところを塞ぎ、その上で、水やりのタイミングやその時の量を工夫する必要がある。
量×単価の売上式を、分解すると「取引客数(漏れを防ぐ)×取引率(水やりのタイミング)×取引単価(水の量)」になる。この3要素が売上アップ(回復)の要件である。
売上アップには、新規客の獲得という回答は正解ではあるが、満点とは言い難い。新規客を獲得するのは容易ではない。お金もかかるし、労力も必要だ。車検のチラシを考えて欲しい。チラシ10,000枚配布して新規が1~3台の入庫であるトヨタ OBD2。
確率0.01~0.03%、チラシ1枚9円(折込料含め)とすれば、9万円かけて最大3台の獲得である。1台当たり3万円かかっているのだ。この3台が次回の車検で入庫してくれる入庫率(回帰率)は、良くて30%、悪いと15%前後である。30%としても3台のうち1台しか入庫してくれないのだ。それでも新規客獲得をやりますか?
この新規の獲得費用が、自社の車検基本料金を超えるようだたっら、止めた方がいいというのが、私の基準である。基準を緩めても、車検平均工賃単価を超えるようだたっら、止めるべきだ。
それよりも、取引客数の中の管理客(現取引客)の脱落防止策と、「取引率」および「取引単価」を改善すべきである。理想かもしれないが、この三つを改善すれば、新規客獲得の必要性はなくなるかもしれない。いかがだろうか、本質的な自社の来年の経営課題が掴めてきただろうか。
個人カーリースが順調だ!
OBD2診断ツール 日産故障診断機
それを踏まえて、今後の経営の重点課題は何かと聞いたところ、
第一位:新規客の開拓(47%)
第二位:営業力の向上(30%)
第三位:優秀な人材の確保(21%)
第四位:技術力の向上(20%)
第五位:従業員の能力開発(15%)
同 :生産性の向上(15%)
となっている。
売上アップの命題に対する答えの第一位が「新規客の開拓」を挙げている。減った管理客を補充するために、新規客の開拓が必要と考えていることになる。売上は、単純に「量×単価」で求められるから、要素の一つである「量」を増やすことは当然であるBMW診断機。
しかし、チョット安直過ぎてはいないだろうか。むしろ、減った理由を改善すべきことが第一位に来るのが本来ではないだろうか。水漏れしている器に、何ぼ水を継ぎ足しても器は満杯にはならない。

水を満杯にするには、まず漏れているところを塞ぎ、その上で、水やりのタイミングやその時の量を工夫する必要がある。
量×単価の売上式を、分解すると「取引客数(漏れを防ぐ)×取引率(水やりのタイミング)×取引単価(水の量)」になる。この3要素が売上アップ(回復)の要件である。
売上アップには、新規客の獲得という回答は正解ではあるが、満点とは言い難い。新規客を獲得するのは容易ではない。お金もかかるし、労力も必要だ。車検のチラシを考えて欲しい。チラシ10,000枚配布して新規が1~3台の入庫であるトヨタ OBD2。
確率0.01~0.03%、チラシ1枚9円(折込料含め)とすれば、9万円かけて最大3台の獲得である。1台当たり3万円かかっているのだ。この3台が次回の車検で入庫してくれる入庫率(回帰率)は、良くて30%、悪いと15%前後である。30%としても3台のうち1台しか入庫してくれないのだ。それでも新規客獲得をやりますか?
この新規の獲得費用が、自社の車検基本料金を超えるようだたっら、止めた方がいいというのが、私の基準である。基準を緩めても、車検平均工賃単価を超えるようだたっら、止めるべきだ。
それよりも、取引客数の中の管理客(現取引客)の脱落防止策と、「取引率」および「取引単価」を改善すべきである。理想かもしれないが、この三つを改善すれば、新規客獲得の必要性はなくなるかもしれない。いかがだろうか、本質的な自社の来年の経営課題が掴めてきただろうか。
個人カーリースが順調だ!
OBD2診断ツール 日産故障診断機
車検整備商品の特徴を伝える
2015年11月09日
整備工場のメイン商品は「車検」である。
20年度自動車分解整備業実態調査」でみても、そのことは明らかだ。整備売上高に占める車検整備売上高構成比は、専業工場42.2%、兼業工場42.5%、ディーラー34.6%となり高い依存率となっている。
そのメイン商品である車検の商品特徴は、なんですか?と質問されたらどう説明しますか?
ある大手整備工場であるA社は、年間1200台強の車検台数を実施していてる。このA社は、2つの車検メニューを持っている。 一つは「立会車検(軽の基本料金8,400円」、もう一つは「預かり車検(同16,800円)」である。
このA社に、私がお客に成りすましてTELコールをし、ミステリーショッパーを試みたた。少々問答を省略しているがやり取りは以下のとおりOBD2アダプター。
『HPを見ているんですが、立会車検と預かり車検の基本料金が違いますが、違いの内容を聞かせてください』 『はい、点検項目が違います。』『点検項目が違うとは?』『立会車検は60箇所の点検をします。預かり車検は120箇所を点検します。』『点検項目の内容は』『詳細は分かりません』『その差は、車検にどう関係するんですか』『どちらも車検は、大丈夫です。』
この返答でお客さまは料金差を納得して予約をしてくれるだろうか?私は、大いに疑問である。なぜこの程度の回答しかできないのか?それは、担当者が車検商品の特徴を理解、把握できていないことに尽きる。もっといえば、車検の特徴を踏まえた料金になっていないのである。

これは、他人事ではない。貴社のフロントは自社の車検の特徴を、要領よく分かりやすく伝え、お客さまに理解・納得をいただける説明ができているだろうか。社内で試していただきたい。
商品特徴を相手に伝える場合は、特徴を2~3つぐらいにまとめること。その特徴を箇条書き的に回答できるようにすること。次に、予想される質問を列挙し、回答を予め用意しておくことが必要であるMaxiDAS DS708。
特徴や回答等を作成する場合、車検のように法律と関連性が強い商品の場合、うかつに説明できない内容もある。したがって、車両法および消費者保護法の関連も含めて、説明内容を組み立てること。
こうして作った話法が、どれだけ担当者のものになているかを、定期的に社内ロープレを実施してチェックし、レベル合わせと、レベルアップを図ることだ。当然、不都合な部分があれば、即座に修正すること。後で修正は、修正いならないので注意してほしい。
KESS OBD Tuning Kit 自動車OBDのチューニングキット
Mini VAG505 VW/AUDI 専門車故障スキャンツール
20年度自動車分解整備業実態調査」でみても、そのことは明らかだ。整備売上高に占める車検整備売上高構成比は、専業工場42.2%、兼業工場42.5%、ディーラー34.6%となり高い依存率となっている。
そのメイン商品である車検の商品特徴は、なんですか?と質問されたらどう説明しますか?
ある大手整備工場であるA社は、年間1200台強の車検台数を実施していてる。このA社は、2つの車検メニューを持っている。 一つは「立会車検(軽の基本料金8,400円」、もう一つは「預かり車検(同16,800円)」である。
このA社に、私がお客に成りすましてTELコールをし、ミステリーショッパーを試みたた。少々問答を省略しているがやり取りは以下のとおりOBD2アダプター。
『HPを見ているんですが、立会車検と預かり車検の基本料金が違いますが、違いの内容を聞かせてください』 『はい、点検項目が違います。』『点検項目が違うとは?』『立会車検は60箇所の点検をします。預かり車検は120箇所を点検します。』『点検項目の内容は』『詳細は分かりません』『その差は、車検にどう関係するんですか』『どちらも車検は、大丈夫です。』
この返答でお客さまは料金差を納得して予約をしてくれるだろうか?私は、大いに疑問である。なぜこの程度の回答しかできないのか?それは、担当者が車検商品の特徴を理解、把握できていないことに尽きる。もっといえば、車検の特徴を踏まえた料金になっていないのである。

これは、他人事ではない。貴社のフロントは自社の車検の特徴を、要領よく分かりやすく伝え、お客さまに理解・納得をいただける説明ができているだろうか。社内で試していただきたい。
商品特徴を相手に伝える場合は、特徴を2~3つぐらいにまとめること。その特徴を箇条書き的に回答できるようにすること。次に、予想される質問を列挙し、回答を予め用意しておくことが必要であるMaxiDAS DS708。
特徴や回答等を作成する場合、車検のように法律と関連性が強い商品の場合、うかつに説明できない内容もある。したがって、車両法および消費者保護法の関連も含めて、説明内容を組み立てること。
こうして作った話法が、どれだけ担当者のものになているかを、定期的に社内ロープレを実施してチェックし、レベル合わせと、レベルアップを図ることだ。当然、不都合な部分があれば、即座に修正すること。後で修正は、修正いならないので注意してほしい。
KESS OBD Tuning Kit 自動車OBDのチューニングキット
Mini VAG505 VW/AUDI 専門車故障スキャンツール